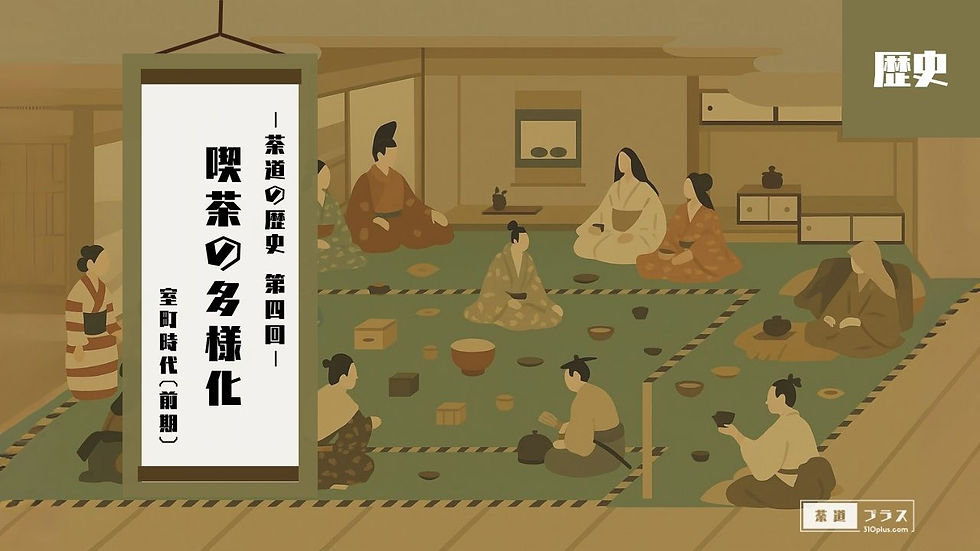1-1|茶のはじまりを辿る ~茶は命の薬草?~|第1回 茶のはじまり|紀元前|茶道の歴史
- ewatanabe1952
- 2023年1月4日
- 読了時間: 7分
更新日:7月20日
―
全10回
茶道の歴史
―
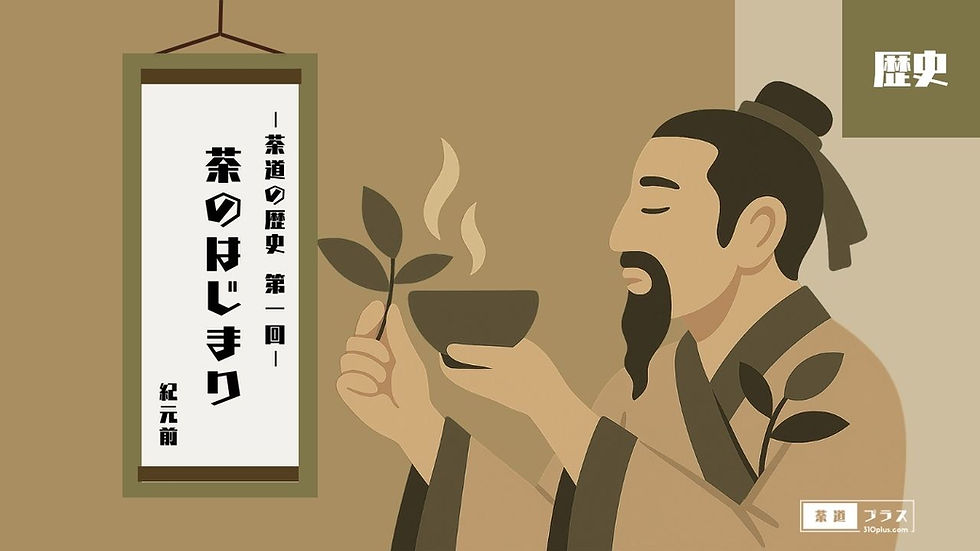
―
―
―
―
―
一碗の抹茶から遡る茶道の歴史
今日、私たちが手にする一服の“抹茶”には、自然の恵みと人々の営み、そして古の知恵が静かに宿っています。
もしその一碗が、約五千年前の知恵の結晶だったとしたら――。
この連載では、現代の茶道につながる“茶”が、どのように生まれ、伝えられてきたのか。その長い歴史をひもといていきます。
第1回のテーマは、「茶のはじまり」。
その起源を、古代中国の神話と医学書の記録から見ていきます。
10―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
古代神話に見る神農大帝と薬草伝説

今日、私たちが喫する一服の“抹茶”の起源を調べるには、“抹茶”として精製される以前の“茶(茶葉)”そのものの歴史をたどる必要があります。
“茶”の起源を知るためには、遥か――5,000年も昔の古代・中国に伝わる神話の世界にまで遡らなければなりません。
“茶”に関するもっとも古い記録とされるのは、古代・中国の神農時代**に登場する三皇五帝**の一人で“医療(漢方)”や“農耕”の神とされる神農大帝**にまつわる神話となります。
神農大帝は人々の病や毒に苦しむ姿を見て、山野の草木を自ら試し、薬効を確かめたと伝えられており、そのひとつが前漢時代(紀元前206年-8年)の淮南王**・劉安**が学者を集めて編纂させた哲学書『淮南子**』に以下のように記されています。
❝❝❝
―原文― 古者、民茹草飲水、采樹木之實、食蠃蠬之肉。 時多疾病毒傷之害、於是神農乃始教民播種五穀、相土地宜、燥濕肥墝高下、嘗百草之滋味、水泉之甘苦、令民知所辟就。 當此之時、一日而遇七十毒。 ―現代訳― 昔、人々は草を煮て食べ、水を飲み、木の実を採り、貝や虫の肉を食べていた。そのため、しばしば病や毒により害を受けていた。 そこで神農は、人々に五穀を播き育てることを教え、土地の性質、乾燥や湿り気、肥えた土ややせた地、高低などに応じた耕作法を示した。 また、自ら百種の草の味や泉水の甘苦を味わい、人々が避けるべきものと摂るべきものを見分けられるようにした。 そのような時、神農は一日に七十もの毒にあたることもあったという。
❞❞❞
神農大帝が自ら試した多くの薬草の効能は、中国・後漢時代(25年-220年)~三国時代(184年-280年)に成立した医学書『神農本草経**』に集約されました。
その後、この書を底本として南朝時代(420年-589年)の医学者・陶弘景**によって整理・編纂され医学書『神農本草経注**』という名で後世に伝えられるようになります。
その『神農本草経』には前述の『淮南子』と同様に以下の記述が見られます。
❝❝❝
―原文― 神農嘗百草 日遇七十二毒 得荼而解之 ―現代訳― 神農は百の草を自ら舐め、一日に72の毒にあたったが、“荼”によって解毒した
❞❞❞
このことから、神農大帝は命をかけて草を食べ、毒にあたっては、それを解毒する術を模索していたことがわかります。
またこの時代には今日の“茶”という文字がまだ確立されておらず―苦菜―を意味する“荼(と/にがな)”の字が使用されていました。
“荼”というものが今日の“茶”と同じであるという確証はないものの時代を経て文字としても“茶”に置き換わっていることから当時の“荼”は今日の“茶”と推測することができます。
このことから“茶”の起源は今から5,000年前の紀元前2700年前頃の神農時代まで遡るとされ、当時の“荼”は今日のように飲料として楽しまれるものではなくその葉を噛んだり、煎じたりして、薬草として用いられていたと考えられています。
世界最古の茶書『茶経』に見る神農大帝
前述した神農大帝の物語に加え、唐時代(618年―907年)の文筆家・陸羽**が8世紀中頃に著した世界最古の茶専門書『茶経**』にも、神農大帝に関する記述が見られます。
❝❝❝
―原文― 茶之為飲、発乎神農氏 ―現代訳― 茶を飲料として用いる習慣は神農に始まる
❞❞❞
ただし、この記述はあくまで伝説的なもので、神農大帝が具体的にどのように茶を飲んでいたのか、また喫茶の習慣がいつ頃から広まったのかについては、明確にはされていません。
茶とは査ことである
「茶」という言葉の由来には、「査(しらべる)」に通じるという説があります。
中国語では「査(チャー)」と「茶(チャー)」の発音が同じであり、神農大帝が草を“調べた”行為が語源になったとされています。
また、現在も使われている「茶渣(ちゃさ)」という言葉は、茶を飲んだ後の残りかす=“茶殻”を意味しますが、これは茶の品質や効能を“調べる”ために使われたことが語源とされています。
「茶底」という言葉もあり、これは茶を完全に出しきった後の“底に残った茶葉”を指します。
医学書に記された茶の性質と薬効

前述の医学書『神農本草経』では365種類の薬物を“上品”・“中品”・“下品”の三類に分類し、それぞれの“性質”“薬効”などを詳しく記しています。
その中には以下のようなに“茶”に関する記述がみられます。
❝❝❝
―原文― 茶味苦、飲之使人益思、少臥、軽身、明目 ―現代訳― 茶の味は苦く、飲むと思考を深め、体は軽くなり睡眠が少なく目も覚める
❞❞❞
このように、すでにこの時代には“茶”が心身を整える効果のある薬草として用いられていたことが伺えます。
茶道の歴史を学べば、よりよい一服に

今日では嗜好品として親しまれている一服の“茶”も、その出発点は命を守る薬草でした。
茶道の歴史を学ぶことは心を込めて点てられた一碗を手にし、注がれた緑豊かな“抹茶”を見た時にその背後にはある数千年に及ぶ人々の叡智と祈りが宿っていることを知ることでよりよい一服を味わうことができるのではないでしょうか―。
次回は、神話の中の“茶”がどのように現実の中の“茶”として登場するのかをご紹介します。
登場人物
神農大帝
生没年不詳|医療神|農耕神|三皇五帝の1人|
劉安
BC179年―BC122年|皇族|学者|淮南王|哲学書『淮南子』の主著者|
陶弘景
456年―536年|医学者|道教「茅山派」の開祖|
用語解説
神農時代 とは
―しんのうじだい― 神農時代とは、中国古代の伝説上の時代で、神農と呼ばれる帝王が治めたとされる時期を指します。神農は「農業の神」または「薬の祖」として知られ、五穀の栽培を教え、人々に農耕の技術を広めたと伝えられています。また、さまざまな草木を自ら口にして薬効や毒性を確かめ、医薬の基礎を築いたともいわれ、『神農本草経』という古代の薬物書にその名が残されています。神農時代は歴史的な実在が確認されたものではなく、黄帝などと並ぶ神話時代の一部とされますが、中国文化や思想においては文明のはじまりを象徴する理想的な時代とされ、特に農業や医学の起源に関する象徴的存在として重要視されています。
三皇五帝 とは
―さんこうごてい― 古代中国の神話伝説時代における8人の帝王で、該当する人物は書物により、さまざまな説が存在するが「伏羲」「女媧」「神農」の3人の半人反妖の姿をした神(三皇)と「黄帝」「顓頊」「嚳」「尭」「舜」の5人の聖人君主(五帝)を指す。 秦の始皇帝は全国を統一した後、「三皇の道徳を兼ねて、五帝の功労を超えた」と「皇」と「帝」二つの名を合わせ今日においても君主としての最高位として用いられる「皇帝」号とした。
神農大帝 とは
―しんのうだいてい― 三皇五帝、三皇の内の一人で、他の三皇「伏羲」「女媧」の亡き後にこの世を治めた神。龍神と人間との間に生まれ、体は人間、頭は牛、身の丈は3mとされる。 人々に医療と農耕を教えたことから「神農大帝」と称され120歳まで生きたとされる。今日においても広く信仰されている。
淮南王 とは
―わいなんおう―
劉安 とは
―りゅう・あん―
淮南子 とは
―えなんじ―
神農本草経 とは
―しんのうほんぞうきょう― 中国最古の本草書(医学書)。その名は中国伝説の三皇五帝の一人で医療の祖とされる「神農」に由来する。 1年の年数に合わせ365品の薬物を「上品(120種)=養命薬」「中品(120種)=養性薬」「下品(125種)=治病薬」と薬効別に分類し記している。 中国医学において『黄帝内経』『傷寒雑病論』とともに、三大古典の1つとされる。
陶弘景 とは
―とう・こうけい―
神農本草経集注 とは
―しんのうほんぞうきょうしっちゅう―
陸羽 とは
―りくう―
茶経 とは
―ちゃきょう―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―