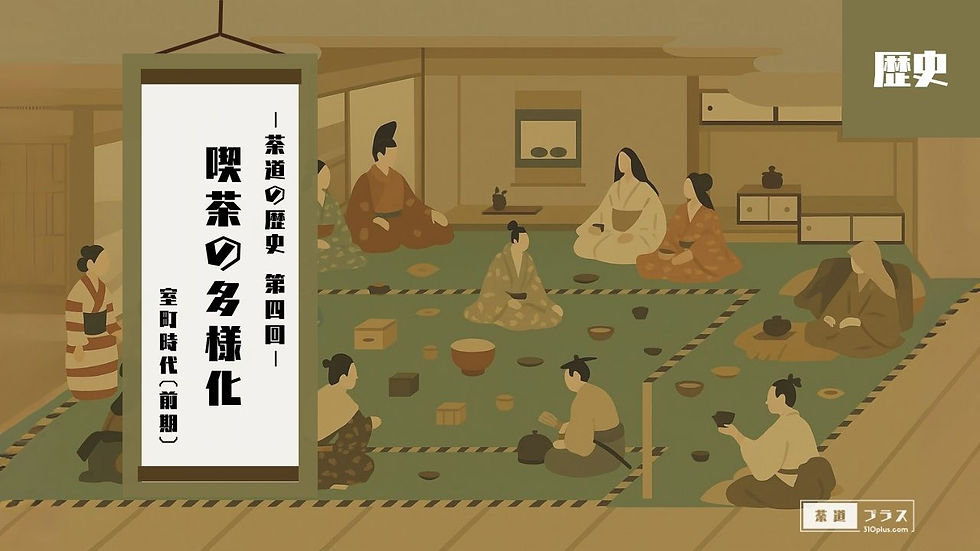1-2|茶の登場 ~正史が語る最古の一服~|第1回 茶のはじまり|紀元前|茶道の歴史
- ewatanabe1952
- 2023年1月5日
- 読了時間: 4分
更新日:7月21日
全10回
茶道の歴史

正史に現れた“茶”の記憶―神話の世界から現実の世界へ
前回ご紹介した神農大帝*による茶の発見は、あくまでも神話上の物語でした。
今回は歴史の記録、つまり正史における“茶”の初登場をひもといていきます。
現存する史料のなかで、最も古く“茶”に言及された文献とは―。
そこに記された言葉が、“茶”の文化の原点を私たちに静かに語りかけてくれます。
神話から抜け出した最古の一服

“茶”が神話から抜け出し、歴史の表舞台に現れるのは、今からおよそ2,000年前の中国・漢王朝時代(BC206年〜220年)となります。
現存する中で“茶”の最古の記録として知られるのが、文学者・王褒*によって書かれた戯文**『僮約**』です。
この作品は、主人が奴隷を雇う際の契約書形式で書かれた文芸作品であり、次のような記述が見られます。
❝❝❝
―原文― 武陽買荼 ―現代訳― 武陽**にて荼を買う
❞❞❞
❝❝❝
―原文― 烹荼盡具 ―現代訳― 茶を煮出し茶具を整える
❞❞❞
この一文から、当時すでに“茶”が商品として売買されていたことを推測することができます。
また、“烹荼(お茶を煮出す)”という行為や“盡具(茶具を整える)”という描写からも、“茶”が日常生活に浸透していたことが読み取れます。
中国・武陽に見る茶の原点

前項の戯文『僮約』の記述によって、“茶”が中国・西南部の武陽において飲用されていたことがわかります。
武陽は古くから“茶葉”の産地として知られ、その風味や品質が高く評価されていたことは、この地域が茶文化発祥の重要な地であることを示しています。
また戯文『僮約』の文中には、“荼”の文字が自然に使われており、すでに“茶”が特別な薬草ではなく、日常の飲料として定着し始めていたことが読み取れます。
茶が文化として昇華していく

文学作品としての『僮約』は、庶民の日常や文化的背景を伝える貴重な史料です。
そこに描かれた“茶”は、もはや神話のなかの霊草**ではなく、日々の暮らしの一部として存在していました。
やがてこの“茶”は、庶民から上層階級や宮廷儀礼の場へと広がり、文化としての“茶”へと成長していくのです。
こうして、“茶”は神話から歴史の歩みをはじめ、やがて日本へと渡り、さまざまな時代と人物の手を経て、今日の“茶道”という世界に誇る唯一の日本固有の文化へと昇華していくこととなります。
次回は、この“茶”はいったいどこで生まれたのか―その謎を追求し“茶”の発祥地を探っていきます。
登場人物
神農大帝
生没年不詳|医療神|農耕神|三皇五帝の1人|
王褒
生没年不詳|文学者|
用語解説
神農大帝 とは
―しんのうだいてい― 三皇五帝、三皇の内の一人で、他の三皇「伏羲」「女媧」の亡き後にこの世を治めた神。龍神と人間との間に生まれ、体は人間、頭は牛、身の丈は3mとされる。 人々に医療と農耕を教えたことから「神農大帝」と称され120歳まで生きたとされる。今日においても広く信仰されている。
王褒 とは
―おうほう― 中国・漢代末期の文学者。風刺を交えた戯文や詩を多く残し、庶民の暮らしや社会風俗を描いた記録として価値が高い。彼の作品『僮約』により、茶に関する最古の記録が残されたとされる。
戯文 とは
―ぎぶん― 漢代に発達した、風刺や滑稽さを含んだ短編の文芸作品。 庶民の生活や時代の風潮を描いた文学形式で、形式にとらわれず自由な表現が特徴。 『僮約』もその一例であり、文学的価値と歴史資料としての価値を兼ね備える。
僮約 とは
―どうやく― 漢代に成立したとされる戯文で、奴隷契約の内容を題材とした文学的な文書。 王褒が著したとされ、当時の庶民生活が生き生きと描かれている。 茶の売買や調理法、茶道具の使用などが記されており、茶文化史上の重要文献である。
武陽 とは
―ぶよう―
霊草 とは
―れいそう―
[人物] 王褒|おうほう
……… 中国・漢代末期の文学者。風刺を交えた戯文や詩を多く残し、庶民の暮らしや社会風俗を描いた記録として価値が高い。彼の作品『僮約』により、茶に関する最古の記録が残されたとされる。
[書物] 戯文|ぎぶん
……… 漢代に発達した、風刺や滑稽さを含んだ短編の文芸作品。
庶民の生活や時代の風潮を描いた文学形式で、形式にとらわれず自由な表現が特徴。
『僮約』もその一例であり、文学的価値と歴史資料としての価値を兼ね備える。
[書物] 僮約|どうやく
……… 漢代に成立したとされる戯文で、奴隷契約の内容を題材とした文学的な文書。
王褒が著したとされ、当時の庶民生活が生き生きと描かれている。
茶の売買や調理法、茶道具の使用などが記されており、茶文化史上の重要文献である。
[地名] 武陽|ぶよう
………
[用語] 霊草|れいそう
………