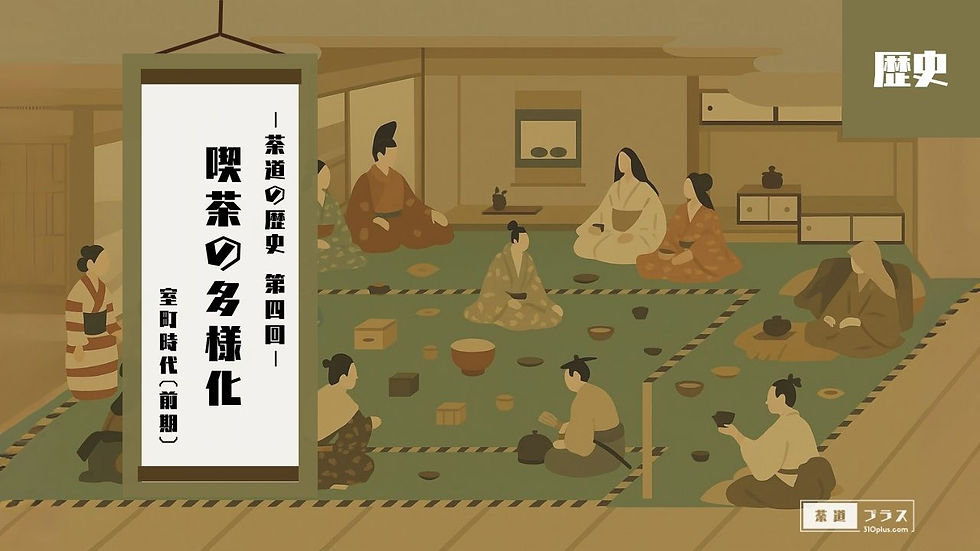2-2|茶会の原点 ~一杯にこめた礼と心~|第2回 茶の渡来|奈良時代~平安時代|茶道の歴史
- ewatanabe1952
- 2023年1月10日
- 読了時間: 4分
更新日:7月21日
全10回
茶道の歴史

一杯にこめた礼と心
一碗の“茶”を、一定の作法でもって人にふるまう。
その所作は今日の“茶会”の原型とされ、日本における喫茶文化のひとつの到達点でもあります。
では、その―“最初の茶会”―は、いつ、どこで、どのように行われたのでしょうか。
今回のテーマは、奈良時代(710年-794年)における宮中行事**に現れる“茶”の姿です。
宮中における引茶の記録
“茶”が日本へ渡来して間もない奈良時代(710年―794年)、実際にどのように飲まれていたのか—。
その詳細は明確に残っていないものの、後世の文献からその実態をうかがい知ることができます。
そのひとつが、室町時代(1336年-1573年)の公卿**・一条兼良*が著した『公事根源**』です。
この書には、天平元年(729年)、「聖武天皇**」が催した宮中行事『季御読経**』において、僧侶に対して「引茶**」がふるまわれたという記録が残されています。
このことから、奈良時代(710年-794年)にはすでに一定の作法を伴う喫茶の風習が存在していたと推測されています。
引茶にみる作法と精神性
引茶とは、当時の団茶**を砕いて粉末状にし、煮立った湯に入れて茶盞に注ぎ、甘葛や生姜で調味して飲む形式の“茶”でした。
この形式には所作や順序が定められており、儀礼性を備えた喫茶として、後世の“茶礼**”“茶会”“茶道”の源流とされています。
さらに、平安時代(794年-1185年)の初めである大同三年(808年)には、平安京**の内裏**東北隅に茶園が設けられ、造茶師が置かれていたという記録も存在します。
これは引茶に供する“茶”を育てるための制度的な取り組みであり、国家レベルで茶文化が芽吹いていた証ともいえるでしょう。
茶が祈りとともにあるということ

『季御読経』は、国家の安泰と天皇の無事を祈る仏教行事であり、東大寺**や興福寺**の高僧**たちを招き、3日から4日にわたって『大般若経**』を読誦**する厳粛な儀式です。
その中で行われた引茶は、単なる飲料としての“茶”のふるまいではなく、仏法修行の一環とされたものであり、“茶”をいただくという行為の中に、心を鎮め、仏に向き合う時間があったことがわります。
茶会という文化の萌芽
宮中でふるまわれた一杯のお茶は、やがて“茶会”という日本独自の文化へと育っていきます。
作法と祈りが結びついたその原点には、単なる飲食を超えた精神性がありました。
次回は、“茶”の栽培がどのようにして日本に根づき、制度や生活に定着していったのかをご紹介してまいります。
登場人物
一条兼良
1402年―1481年|公卿|学者|一条家(五摂家内の一つ)八代当主|
聖武天皇
701年―756年|第四十五代天皇|第四二代文武天皇の第一皇子|
用語解説
宮中行事
―きゅうちゅうぎょうじ―
公卿
―くぎょう―
一条兼良
―いちじょう・かねよし―
公事根源
―くじこんげん― 応永二九年(1422年)頃に一条兼良が著した室町時代の有職故実書。室町時代の宮中の儀式や行事の起源や沿革を記した書物。
聖武天皇
―しょうむてんのう― 701年―756年。奈良時代の第45代天皇。在位中に大仏造立や仏教の保護政策を推進し、国家と宗教を結びつけた。宮中行事「季御読経」の創始者であり、その中で引茶が行われた記録が残る。
季御読経
―きのみどきょう― 「季御読経」は、天平元年(729年)にはじまったとされ平安時代(794年-1185年)の終り頃まで続いた「宮中行事」のひとつ。東大寺や興福寺などの諸寺から60~100の禅僧を朝廷に招き3日~4日にわたって『大般若経』を読経し国家と天皇の安泰を祈る行事であり、その中の第二日目に衆僧に「引茶」をふるまう儀式が行われていました。のちに『[宮中行事]季御読経』は春秋の二季に取り行われることとなったが、「引茶」は春のみに行われていたとされています。また「茶」を喫する事も修行の一つであるという意から「行茶」とも呼ばれていました。
引茶
―ひきちゃ― 茶園で「茶」を挽くという意から、「引茶」の字が用いられる。飲茶方法は「団茶」を砕いて薬研で挽いて粉末状にしたのち沸騰した釜の中に投じ、「茶盞」に注ぎ「甘葛」「生姜」などで調味して飲まれていました。大同三年(808年)平安京、の内裏東北隅に茶園が経営され「引茶」で使うための造茶師が置かれていという。また一定の作法をもって喫することから今日の「茶道」の原型がこの時点で存在していたと考えられます。
団茶
―だんちゃ― 蒸した茶葉を押し固め、団子状に成形した唐代の保存用の茶。煎じて飲まれることが多く、儀礼や薬用にも用いられた。後の抹茶文化や煎茶文化の源流とされる。
茶礼
―されい―
平安京
―へいあんきょう―
内裏
―だいり―
東大寺
―とうだいじ―
興福寺
―こうふくじ―
高僧
―こうそう―
大般若経
―だいはんにゃきょう― 仏教の智慧「般若」の教えを説いた全600巻に及ぶ大乗仏教の根本経典です。唐の玄奘三蔵が訳出し、日本では国家鎮護・災厄除けの祈祷に用いられました。特に「大般若転読法要」は、経巻を勢いよく繰ることで加護を願う儀式として現代にも伝わります。「空」の思想は茶道や禅とも深く関わり、今なお精神文化に大きな影響を与えています。
読誦
―どくじゅ―