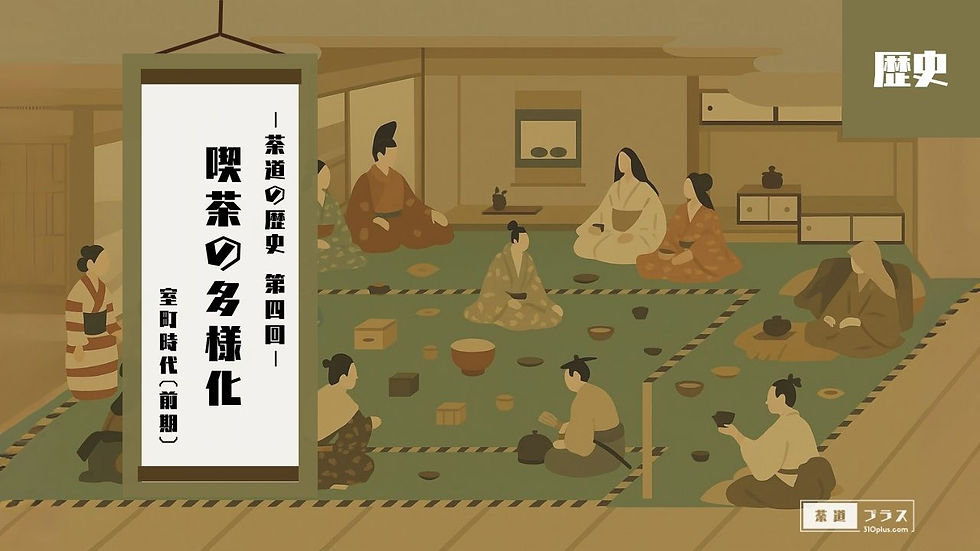2-3|茶園の記憶 ~一粒から広がる茶の文化~|第2回 茶の渡来|奈良時代~平安時代|茶道の歴史
- ewatanabe1952
- 2023年1月11日
- 読了時間: 4分
更新日:7月21日
全10回
茶道の歴史
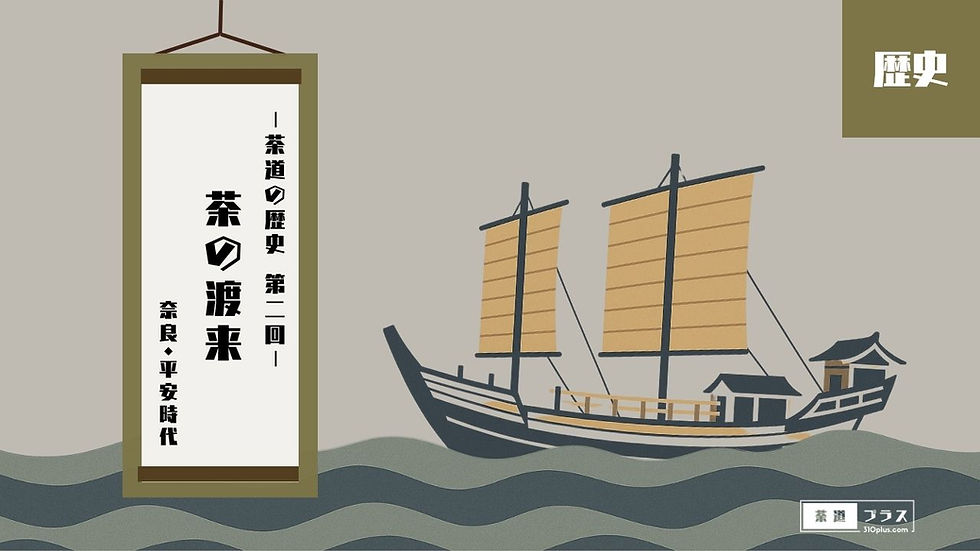
一粒から広がる茶の文化
喫茶の文化が芽吹いたその先には、“育てる”文化が始まります。
日本に“茶”がもたらされたのち、やがてその“茶”は、海を越えて持ち帰られた“種”から、わが国の大地に根を張ることになります。
今回のテーマは、日本で初めて行われた「茶の栽培」について、古文献をもとにひもといてまいります。
最澄が伝えた最古の茶園

これまで、日本に“茶”が渡来し、宮中行事**などで喫されていたことを見てきました。
では、その“茶”はいつ、どこで、どのように栽培されるようになったのでしょうか。
“茶”の栽培に関する最も古い記録の一つが、比叡山**のふもとにある日吉社**の神職**・祝部行丸*が天正十年(1582年)に記した『日吉社神道秘密記**』に残されています。
この書の中で、最澄*が中国・唐**より帰国後、比叡山の麓に茶園を開いたことを記しています。
その茶園は現在、滋賀県大津市坂本に「日吉茶園**」としてその名を残しており、日本最古の茶園として伝承されています。
各地に広がる栽培の痕跡
茶園は比叡山だけではなく、内裏の周辺や、東海地方の三河国などにも茶園が存在したことが、いくつかの史料から知ることができます。
前回紹介した宮中行事「季御読経**」の儀式で供された引茶**には、こうした各地で栽培された“茶”が用いられていたと推測されています。
また、九州地方においても栽培が行われていたことを示す重要な資料が延喜三年(903年)までに編纂された『菅家後集**』です。
菅原道真が語る「一杯の記憶」

『菅家後集』は、菅原道真*が自らの詩文をまとめた漢詩集であり、その中には、自身が九州の大宰府**に左遷された際、“茶”を飲んだという一節が残されています。
❞❞❞
―原文― 悶飲一杯茶 ―現代訳― 悶々とした想いにてい一杯の茶を飲む
❞❞❞
この記述により、九州地方においてもすでに“茶”が栽培され、日常的に喫されていたことが伺えます。
つまり、平安時代(794年―1185年)の初期には、すでに中央・地方を問わず、茶が根づき始めていたということがわ推測されます。
茶は根づき、文化となる

こうして、最澄による茶の栽培が始まり、やがて各地へと広がっていった“茶の栽培”は、貴族や僧侶の間にも受け入れられ、後の茶文化の土台として深く根づいていきます。
古来、人々の手によって大切に育てられた一株の茶樹は、国を越え、時を越え、やがて私たちの一碗へとつながっています。
“茶の栽培”という行為に込められた文化の萌芽は、今日の茶道の礎を成すものとなりました。
今回ご紹介したように、“茶を育てる”という営みは、単なる農耕の始まりではなく、精神文化と日常とをつなぐ“場”を支える基盤として、日本各地に広がっていったのです。
次回は、“茶”という語がどのように公的な記録に現れ、国家の中にどのように記述されていったのかを探っていきます。
登場人物
祝部行丸
生没年不詳|日吉社官職|
最澄
766年―822年|伝教大師|僧|遣唐使|天台宗開祖|比叡山「延暦寺」開山|
菅原道真
845年―903年|貴族|学者|政治家|詩人|学問の神様|
用語解説
宮中行事
―きゅうちゅうぎょうじ―
比叡山
―ひえいざん―
日吉社
―ひよししゃ―
神職
―しんしょく―
祝部行丸
―はりふべ・ゆきまる―
日吉社神道秘密記
―ひよししゃしんどうひみつき― 天正10年(1582年)に日吉大社の神職『祝部行丸』によって記された、日吉社に伝わる神道儀礼や信仰、歴史をまとめた記録。特に、『最澄』が唐より帰国後、比叡山の麓に茶園を開いたという記述があり、これは日本における茶の栽培に関する最古級の文献記録として注目されています。
最澄
―さいちょう― 766年―822年。平安時代初期の僧で、天台宗の開祖。804年に遣唐使として唐に渡り、仏教とともに茶の文化を学び、帰国後は比叡山の麓に日本初の茶園を開いたと伝えられる。平安時代初期の僧で、天台宗の開祖。804年に遣唐使として唐に渡り、仏教とともに茶の文化を学び、帰国後は比叡山の麓に日本初の茶園を開いたと伝えられる。
唐
―とう―
日吉茶園
―ひよしちゃえん― 滋賀県大津市坂本にある日本最古の茶園とされる場所。『日吉社神道秘密記』に最澄がこの地に茶園を開いたと記され、今日に至るまで茶文化の聖地とされている。
季御読経
―きのみどきょう―
引茶
―ひきちゃ―
菅家後集
―かんけこうしゅう― 『菅原道真』によって編まれた漢詩集で、彼の左遷後の心情や風景が詠まれている。茶に関する記述がある最古級の日本文献としても重要。
菅原道真
―すがわらの・みちざね― 平安時代の学者・政治家・詩人で、卓越した学識と文章力により右大臣まで昇進しましたが、藤原氏の讒言により大宰府へ左遷され、失意の中で没しました。死後は怨霊と恐れられ、やがて「天神」として神格化されます。現在では学問の神として広く信仰され、梅を愛したことから茶道でも「飛梅」などの銘に名を残しています。