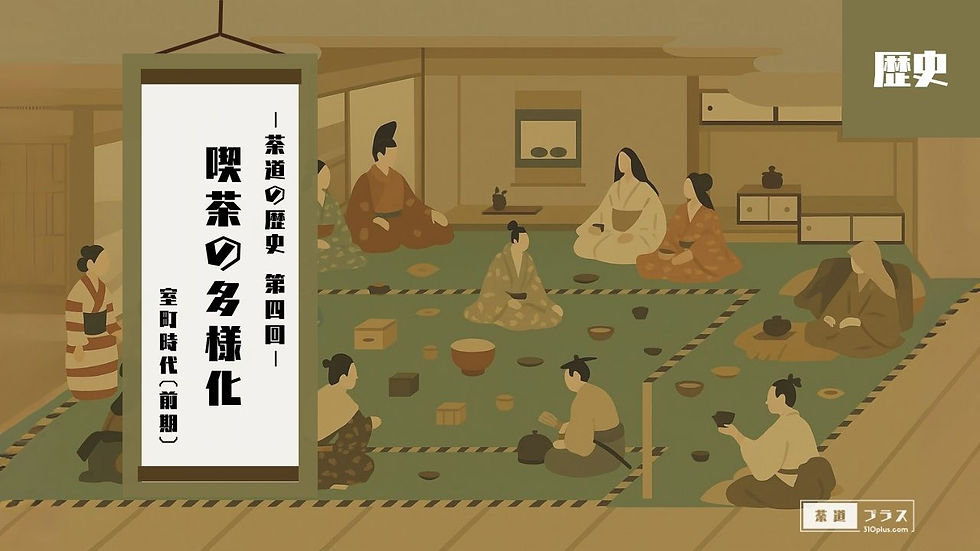2-4|茶の公式記録 ~日本史に刻まれた一碗~|第2回 茶の渡来|奈良時代~平安時代|茶道の歴史
- ewatanabe1952
- 2023年1月12日
- 読了時間: 4分
更新日:7月21日
全10回
茶道の歴史
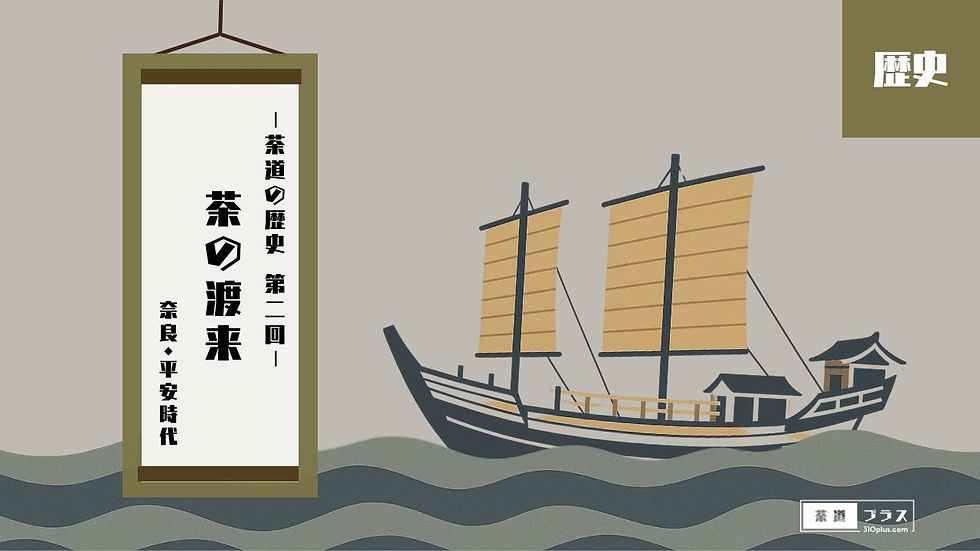
日本史に刻まれた一碗
“茶”が記録として歴史に刻まれる瞬間。
神話や文芸からではなく、国家の公式記録に“茶”の名が現れる。
その一節は、いにしえの天皇と僧侶の間で交わされた一碗の物語からはじまります。
今回は、日本最古の勅撰史書**『日本後紀**』に登場する“茶”について、紐解いていきます。
勅撰史書『日本後紀』に現れた茶の名

これまで紹介してきた『日吉社神道秘密記**』や『菅家後集**』などは、いずれも私的な記録や詩文に基づくものでした。
しかし、“茶”という語が国家の公式文書に初めて登場したのは、承和七年(840年)に成立した勅撰史書『日本後紀』とされています。
『日本後紀』は、奈良時代(710年―794年)末から平安時代(794年―1185年)初期にかけての歴史をまとめた国家の正式な記録であり、その中に“茶”に関する最古の記述が見られます。
嵯峨天皇と永忠の一碗

『日本後紀』が記す最古の“茶”に関する記録は、弘仁六年(815年)4月22日の出来事です。
第52代天皇である嵯峨天皇*が、近江の韓崎(現・滋賀県大津市唐崎)に行幸した際、梵釈寺**の住職であった永忠*が、“茶”を煎じて献じたという内容が記されています。
一碗の茶を、天皇に献上したこの出来事こそ、日本史において“茶”という語が公的記録に刻まれた、最も古い事例とされており、まさに日本茶史に刻まれた初めての一碗といえる瞬間です。
またこのときに嵯峨天皇に振る舞われた茶は、引茶**と同様に、団茶**を砕いて煎じたものであり、薬用・儀礼的な目的で用いられたと考えられます。
同時に、それは仏教の修行的文脈に基づいた行為であったことも読み取れます。
茶栽培の奨励と制度化

さらに『日本後紀』には、興味深い続きがあります。
嵯峨天皇は、この行幸のわずか2ヶ月後、諸国の役人に命じて“茶”の栽培を奨励しました。
その対象は「機内(畿内)」「近江」「丹波」「播磨」などで、都(京都)の周辺国に“茶”の木を植え栽培させ“茶”の献上を求めたといいます。
この記述から、平安初期にはすでに―“茶を育て、天皇に献じる”―という制度的な動きがあったことが読み取れます。
これは、“茶”が単なる飲料や輸入品ではなく、“文化資源”として国家的な制度に組み込まれ始めた証拠でもあります。
一碗が文化を動かした

嵯峨天皇と永忠の間で交わされた一碗の“茶”——―。
“茶”が「国の記録」に刻まれたその時、それはもはや異国の贈り物ではなく、日本人の手によって育てられ、扱われ、文化化される運命を持った存在へと変わりました。
嵯峨天皇の一碗の受け取りが、茶道の歴史にどれほど深い根を残したか――。
次回は、こうして芽吹いた茶文化が、遣唐使の廃止とともに一度“衰退”の局面を迎える歴史の転換点について巡っていきます。
登場人物
嵯峨天皇
786年―842年|第五十二代天皇|第五十代桓武天皇の第五皇子|
永忠
743年―816年|僧|大僧正|梵釈寺住職|
用語解説
勅撰史書
―ちょくせんしょし―
日本後紀
―にほんこうき―
日吉社神道秘密記
―ひよししゃしんどうひみつき― 天正10年(1582年)に日吉大社の神職『祝部行丸』によって記された、日吉社に伝わる神道儀礼や信仰、歴史をまとめた記録。特に、『最澄』が唐より帰国後、比叡山の麓に茶園を開いたという記述があり、これは日本における茶の栽培に関する最古級の文献記録として注目されています。
菅家後集
―かんけこうしゅう― 『菅原道真』によって編まれた漢詩集で、彼の左遷後の心情や風景が詠まれている。茶に関する記述がある最古級の日本文献としても重要。
嵯峨天皇
―さがてんのう― 786年―842年。平安時代初期の第52代天皇。文化・文芸を奨励し、「弘仁文化」を築いた人物。近江行幸の折に茶を賜り、茶の栽培を諸国に命じたことで、茶文化発展の礎を築いた。
梵釈寺
―ぼんしゃくじ―
永忠
―えいちゅう― 743年―816年。奈良〜平安時代の僧侶で、梵釈寺の住職。嵯峨天皇に茶を献じた人物として『日本後紀』に記され、日本茶文化史上の重要人物とされる。
引茶
―ひきちゃ― 茶園で「茶」を挽くという意から、「引茶」の字が用いられる。飲茶方法は「団茶」を砕いて薬研で挽いて粉末状にしたのち沸騰した釜の中に投じ、「茶盞」に注ぎ「甘葛」「生姜」などで調味して飲まれていました。大同三年(808年)平安京、の内裏東北隅に茶園が経営され「引茶」で使うための造茶師が置かれていという。また一定の作法をもって喫することから今日の「茶道」の原型がこの時点で存在していたと考えられます。
団茶
―だんんちゃ―