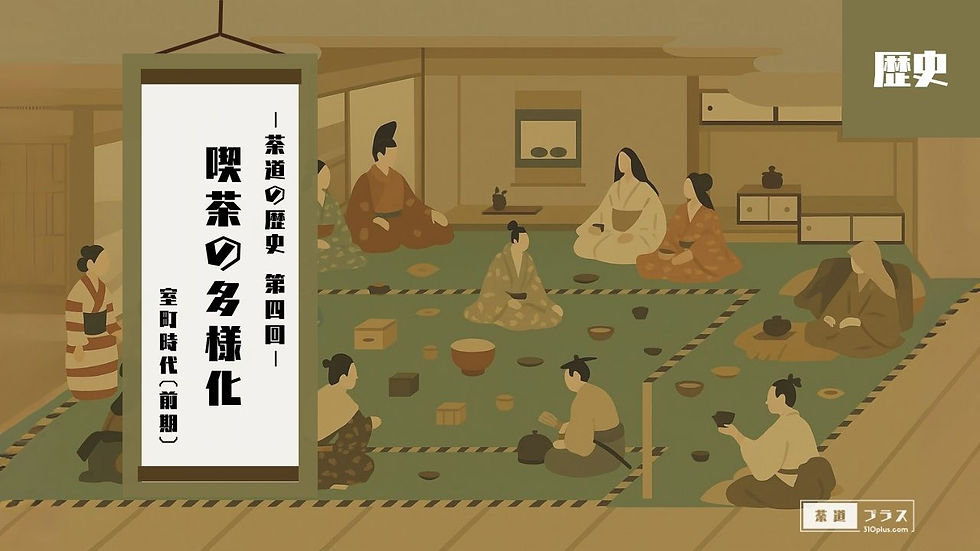3-1|茶の専門書 ~『喫茶養生記』が伝えた智恵~|第3回 喫茶のはじまり|鎌倉時代|茶道の歴史
- ewatanabe1952
- 2023年1月16日
- 読了時間: 4分
更新日:7月21日
全10回
茶道の歴史
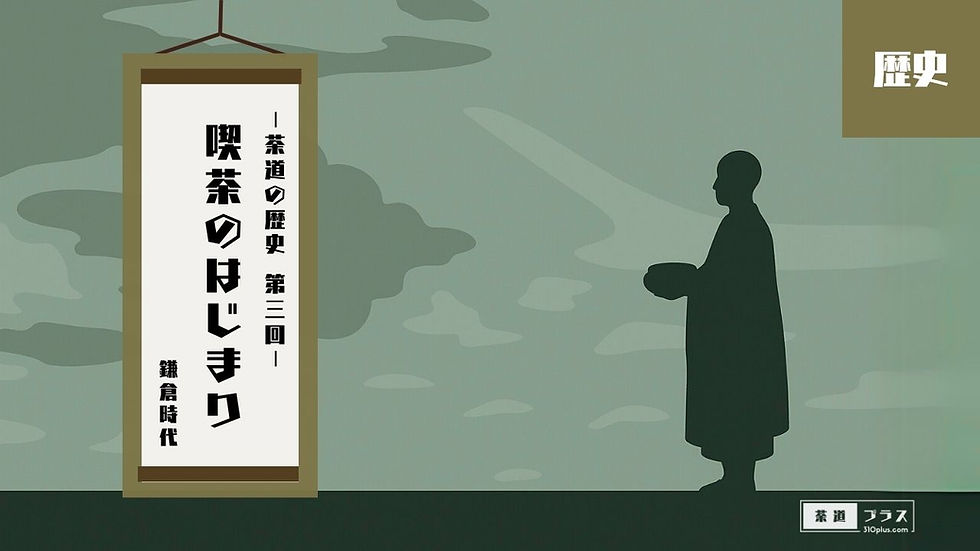
茶は養生の仙薬なり
静寂の中で一服の茶を喫する――。
その所作の背後には―“心を整える”―という、深い目的が込められています。
この―“喫茶の思想”―が、初めて体系として日本にもたらされたのが、鎌倉時代(1185年―1333年)です。
今回は、日本における本格的な「喫茶文化」の確立と、記録に残る最古の専門書『喫茶養生記**』をご紹介します。
栄西が持ち帰った「種」と「思想」

鎌倉時代(1185年―1333年)の初期、建久二年(1191年)――。
臨済宗**の開祖として知られる栄西*は、中国・宋**に渡り、禅宗とともに“抹茶の喫茶法”や“製茶の技術”を学びました。
帰国後、栄西は筑前国(現:福岡県)の背振山**に宋より持ち帰った“茶の種(実)”を植え、日本における本格的な“茶”の栽培を始めたと伝えられています。
しかし栄西が日本の茶文化に残した最大の功績は、文治五年(1211年)に著した“茶”の専門書――『喫茶養生記』の執筆にあります。
喫茶養生記とは

『喫茶養生記』は現存する文献としては日本最古の“茶に関する専用書”であり、喫茶文化の出発点ともいえる貴重な史料となります。
この書物は上下二巻構成で
❝❝❝
・上巻:“茶”の効能や服薬との関係 ・下巻:医学的観点からの喫茶法
が中国医学の知識と仏教思想に基づいて詳述されており、冒頭には次のような一文があります。
❝❝❝
―原文― 茶 養生仙薬** 延齢妙術 ―現代訳― 茶は身体を養う仙人の薬であり、長寿を保つ不思議な術である。
❞❞❞
この言葉には、“茶”が単なる嗜好品ではなく、生命を養う薬としての側面をもって重んじられていたことが表れています。
禅と喫茶の融合

『喫茶養生記』には当時の中国の医学文献が多数引用されており、仏教・医学・食養生の知見を統合した実用的な書でもありました。
なかでも、禅宗**の修行における“茶”の役割は極めて重要視されていました。
長引く仏道修行のなかで、眠気を防ぎ、精神を安定させるための“茶”の効用は、禅宗において非常に重要なものであり、喫茶は禅の修行法の一環でもあったのです。
武士へと広がる文化の芽
栄西はこの書を当時の鎌倉幕府**第三代将軍**・源実朝*に献上し、武士階級にも茶の有用性を伝えようとしました。
それはやがて、“茶”が仏教の枠を超えて広まり、武士社会や一般層へも浸透するきっかけともなっていきます。
このようにして、日本における“喫茶文化”は、鎌倉時代(1185年-1333年)という武家政権の新時代にふさわしく、“禅の精神”とともに静かに、そして力強く根づいていくこととなります。
書と種が遺したもの
静けさとともに心を整える喫茶の作法は、やがて“茶道”として洗練されていきます。
その原点は、一人の禅僧がもたらした“書”と“種”にありました。
次回は、“茶”がどのように薬としても重用され、日常に取り入れられていったのか――その変遷をたどっていきます。
登場人物
栄西
1141年―1215年|明庵栄西|僧|臨済宗開祖|「建仁寺」開山|
源実朝
1192年―1219年|鎌倉幕府三代将軍|源頼朝の子|
用語解説
喫茶養生記
―きっさようじょうき― 1211年に『栄西』によって著された日本最古の茶専門書。茶の効能、製法、薬効などを仏教医学的観点から記し、武士や僧侶に茶の重要性を説いた。上下二巻構成。
臨済宗
―りんざいしゅう―
栄西
―えいさい― 1141年―1215年。鎌倉時代初期の臨済宗の開祖であり、日本に本格的な禅宗を伝えた僧侶です。2度にわたって宋に渡り、禅の教えとともに茶の種子と喫茶の習慣を日本に持ち帰りました。著書『喫茶養生記』では茶の効能を説き、茶文化の発展にも大きく貢献しました。建仁二年(1202年)将軍源頼家が寺域を寄進し栄西禅師を開山として宋国百丈山を模して「建仁寺」を建立。
宋
―そう―
背振山
―せふりやま―
仙薬
―せんやく―
禅宗
―ぜんしゅう―
鎌倉幕府
―かまくらばくふ―
武将
―ぶしょう―
源実朝
―みなもとの・さねとも― 1192年―1219年。鎌倉幕府第三代将軍。源頼朝の子で、政治よりも文化・和歌に深い関心を持ち、歌人としても高名。仏教や漢詩にも通じた教養人であり、『明菴栄西』が著した『喫茶養生記』を献上されたことで知られ、武士階級に茶の効能が伝わる契機となった。