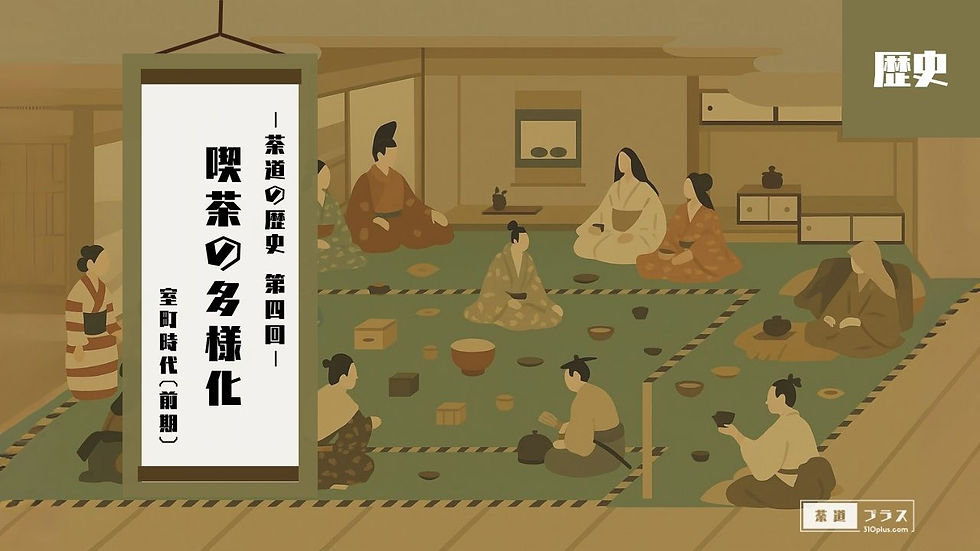3-3|茶園の広がり ~栂尾から始まる名産地の系譜~|第3回 喫茶のはじまり|鎌倉時代|茶道の歴史
- ewatanabe1952
- 2023年1月18日
- 読了時間: 5分
更新日:7月21日
全10回
茶道の歴史
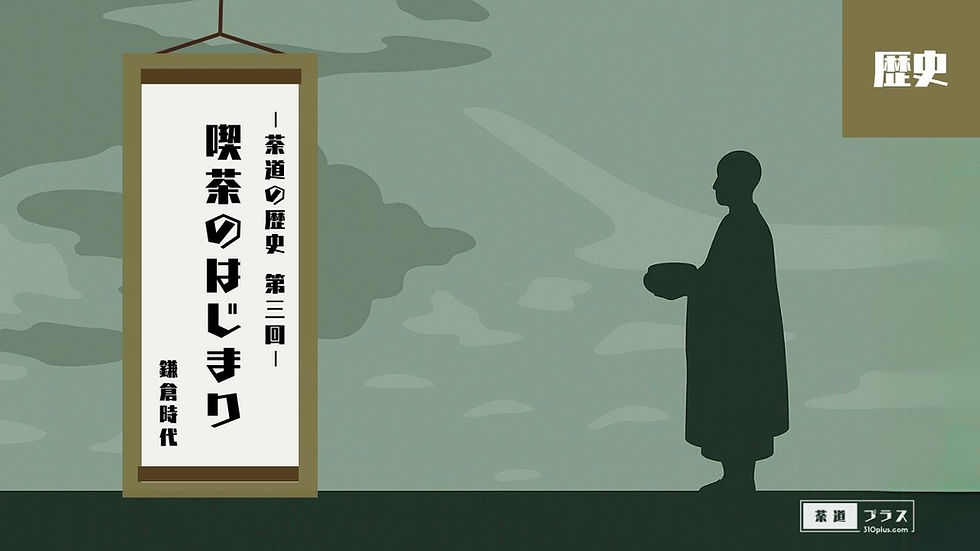
茶が根づく
“茶”が、土地に根を張る――。
それは、僧たちの手により静かに蒔かれ、やがて名産地として花開いた―“文化の芽”―でした。
薬としての“茶”が、栽培という実践を通じて人々の暮らしの中に浸透していった鎌倉時代(1185年―1333年)。
今回は、その茶園の広がりと名産地誕生の物語をたどります。
明恵と宇治茶のはじまり

鎌倉時代(1185年―1333年)、“茶”の薬用効果が広く認識されるとともに、“茶”を飲む習慣は近畿を中心に徐々に全国へと広がっていきました。
特に注目されたのが京都・栂尾**の高山寺**の僧・明恵*です。
明恵は栄西*より譲り受けた“茶”をこの地で栽培し、後の「宇治茶**」の基礎を築いたとされています。
さらにこの“茶”は明恵の手によって「伊勢国(三重県)」「駿河国(静岡県)」「武蔵国(東京周辺)」へと“茶”の栽培が広がり、今日ではこれらの地はいずれも日本有数の茶の名産地として知られています。
大茶盛と叡尊の茶文化

奈良・真言律宗**総本山「西大寺**」の第一世長老「叡尊*」は、延応元年(1239年)の正月に行われた年始修法の結願日に、西大寺復興の感謝を込めて鎮守八幡神社に供茶した行事の余服の“茶”を多くの衆僧に振る舞いました。
この儀式は、現在も西大寺で行われている「大茶盛**」の起源とされています。
この大茶盛の儀式には二つの大きな意義がありました。
ひとつは、―戒律**復興―を目的とし、―不飲酒戒**―の実践として、酒盛の代わりに茶盛を行ったこと。
もうひとつに、―“民衆救済”―の一環として、当時高価な薬とされていた“茶”を施茶**することで、医療・福祉の実践を示したことです。
日本各地へ広がる銘茶の産地

叡尊が弘長二年(1262年)二月から八月にかけて鎌倉に下向した際の活動を、弟子の性海**が綴(つづ)った日記『関東住還記*』には旅の途中で「近江」「守山」「美濃」「尾張」「駿河」「伊豆」などの九カ所で「諸茶**」を行ったと記録されています。
しかし、高齢での長旅を考えると、布教や施茶であると同時に、長旅を支える自らの栄養補給や薬用として飲んだ可能性も高いと考えられます。
その後、南北朝時代(1336年―1392年)に臨済宗**の僧である虎関師錬*が著した『異制庭訓往来*』には、当時の銘茶の産地として「京都各地」「大和」「伊賀」「伊勢」「駿河」「武蔵」が記されています。
これにより、鎌倉時代(1185年―1333年)末期から南北朝時代(1336年―1392年)にかけて、寺院を中心とした茶園が関東へと広がり、“茶”の栽培が普及するとともに、“茶”を飲む習慣が一般の間にも広がっていったことを示しています。
名産地のはじまりと精神文化への移行

“茶”はこの時代を経て、薬草から文化へと姿を変え始めることとなります。
土地に根づいた“茶”の文化は、やがて“道”として総合芸術へと育っていきます。
一粒の“茶”の実が生み出した名産地の広がりは、私たちの一碗の背後にある物語のはじまりでした。
次回は、“茶”と“禅”の融合がもたらした―“精神文化としての喫茶”―についてご紹介します。
登場人物
明恵
1173年―1232年|明恵上人|僧|華厳宗中興の祖|栂尾山「高山寺」開山|
栄西
1141年―1215年|明庵栄西|僧|臨済宗開祖|「建仁寺」開山|
叡尊
1201年―1290年|僧|真言律宗総本山『西大寺』第一世長老|西大寺中興の祖|
性海
生没年不詳|叡尊の高弟|
虎関師錬
1278年―1346年|本覚国師|僧|臨済宗|五山文学の第一人者|
用語解説
栂尾
―とがのお―
高山寺
―こうさんじ―
明恵
―みょうえ―
栄西
―えいさい―
宇治茶
―うじちゃ―
真言律宗
―しんごんりっしゅう―
西大寺
―さいだいじ―
叡尊
―えいそん―
大茶盛
―おおちゃもり― 延応元年(1239年)1月16日、真言律宗総本山『西大寺』の第一世長老『叡尊』が西大寺復興の感謝を込めて鎮守八幡に供茶した行事の余服茶を多くの衆僧に振る舞ったことに由来する茶儀。これらの理念は800年近く受け継がれ、今日も春秋の大茶盛式として4月第2土日と10月第2日曜に開催されています。 戒律の本質である「一味和合」の精神を体現する儀式として、両手で抱え顔が隠れるほどの大きな茶碗を回し飲みし、連客と助け合いながら結束を深める宗教的な茶儀です。
戒律
―かいりつ―
不飲酒戒
―ふおんじゅかい―
施茶
―せちゃ―
性海
―しょうかい―
関東往還記
―かんとうおうかんき― 真言律宗総本山『西大寺』の第一世長老『叡尊』が、弘長二年(1262年)に鎌倉へ赴いた際の旅の記録。弟子の『性海』により記されたもので、旅の行程や「諸茶」などが記され、当時の茶文化を知る上での重要史料である。
諸茶
―もろちゃ―
臨済宗
―りんざいしゅう― 臨済宗は、中国・宋代の禅僧・臨済義玄を源流とする禅宗の一派で、日本には鎌倉時代初期に栄西によって伝えられました。鎌倉・室町幕府の庇護を受け、五山制度のもと学問や文芸の中心となり、武家文化と深く結びつきました。坐禅や公案による修行で直観的な悟りを目指し、「不立文字」「直指人心」の理念を重視します。茶道にも強い影響を与え、千利休ら茶人は禅の精神を茶の湯の根底に据え、静寂と無駄のない所作に深い精神性を表現しました。
虎関師錬
―こかん・しれい―
異制庭訓往来
―いせいていきんおうらい― 南北朝時代に『虎関師錬』によって著された往来物。礼法や知識をまとめた教養書であり、当時の銘茶産地が記されている。寺院を中心とした茶園の広がりや、各地における茶文化の浸透を裏付ける資料のひとつ。