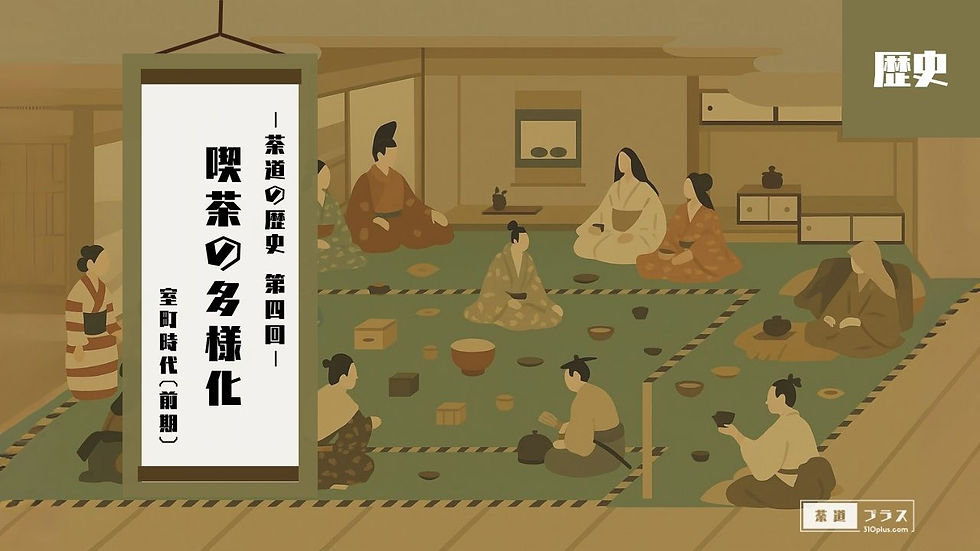3-4|禅と茶の道 ~心を調える喫茶の教え~|第3回 喫茶のはじまり|鎌倉時代|茶道の歴史
- ewatanabe1952
- 2023年1月19日
- 読了時間: 4分
更新日:7月21日
全10回
茶道の歴史

喫茶の教え
“茶”は、ただの飲み物ではなかった――。
それは“禅**”と出会い、深い精神性と結びついていく—。
一服の“茶”に心を調え、己を見つめる。
今回は、“茶”が“禅”と融合し、喫茶文化として花開いていく姿をたどります。
禅苑清規と喫茶法の受容

鎌倉時代(1185年―1333年)、日本における“茶”は“禅”と出会い、精神修養のための道具としての性格を強めながら広がっていきました。
すでにご紹介したように、、栄西*によってもたらされた「喫茶法**」は、単なる薬用にとどまらず、禅の教えと深く結びついた実践でした。
当時の中国・宋時代(960年―1279年)の禅寺**では、寺院生活の規範を定めた『禅苑清規*』が整備されており、その中には「茶礼**」に関する詳細な作法や規律も含まれていました。
この『禅苑清規』は、中国・唐時代(618年―907年)の禅僧・百丈懐海**が定めたとされる『百丈清規**』をもとに、中国・宋時代の長蘆宗賾**によって編纂されたもので、現存する最古の清規**として知られています。
『禅苑清規』では、僧侶の日常作法や叢林**の職制、修行の秩序が厳格に定められ、喫茶は単なる飲食ではなく、心身を清め、修行の一環として位置づけられていました。
こうした教えは、宋の禅僧**たちによって実践され、日本の禅僧たちにも受け継がれ、茶の文化と禅の精神が深く結びついていく大きな基盤となったのです。
禅苑清規の定着

禅僧の道元*は栄西の弟子「明全*」とともに宋へ渡り、四年の修行を経て帰国。
その後、越前に『永平寺**』を開創し、曹洞宗**を広めました。
道元が持ち帰った“禅”の精神と作法は、“喫茶法”とも融合し、禅院における喫茶の規範を日本に根づかせるきっかけとなりました。
また京都・紫野『大徳寺**』の開祖「宗峰妙超*」の師である「南浦紹明*」も文永四年(1267年)に帰国していることからも前述の“禅苑清規”が確実に日本へと定着していったことが推測されます。
これらの動きにより、“禅苑清規”に基づく“喫茶法”が、日本でも禅宗寺院において自然と受け入れられ、定着していったと考えられます。
武士階級への浸透

また“茶”は禅宗寺院と同じく、鎌倉武士の中にも浸透していきました。
鎌倉幕府**第三代将軍**・源実朝*をはじめとする将軍達が茶を嗜んでいたことや禅宗**の広まりとともに“茶”と“禅”の結びつきはより強固なものとなりました。
その結果“喫茶法”は精神修養の側面を強めながら日本各地に広がり普及すると共に喫茶文化の確立へとつながっていきます。
このようにして、“茶”と“禅”は分かちがたく結びつき、日本の精神文化の核をなす存在へと成長していくこととなります。
喫茶の思想と茶道の原型

“茶”は心を整える教養として、禅の教えとともに深く根を下ろし、のちの“茶道”の原型となる静かな力を育んでいきました。
“茶”を点て、静かにいただく――その所作の奥にあるのは、己を見つめる時間です。
“禅”とともに育まれた喫茶の思想は、のちの“茶道”の核心に宿り、今もなお私たちの暮らしに静かな光を灯しています。
次回は、喫茶文化が武家から町衆へ広がっていく様子を見ていきます。
登場人物
栄西
1141年―1215年|明庵栄西|僧|臨済宗開祖|「建仁寺」開山|
百丈懐海
749年-814年|大智禅師|僧|洪州宗|
長蘆宗賾
生没年不詳|慈覚大師|僧|雲門宗|
道元
1200年―1253年|僧|高祖承陽大師|曹洞宗の開祖|「永平寺」開山|
明全
1184年―1225年|僧|臨済宗黄龍派|
宗峰妙超
1283年―1338年|大燈国師|僧|臨済宗|「大徳寺」開山|
南浦紹明
1235年-1308年|大応国師|僧|臨済宗|
源実朝
1192年―1219年|鎌倉幕府三代将軍|源頼朝の子|
用語解説
禅
―ぜん―
栄西
―えいさい―
喫茶法
―きっさほう―
禅寺
―ぜんでら―
禅苑清規
―ぜんえんしんぎ―
茶礼
―されい―
百丈懐海
―ひゃくじょう・えかい―
百丈清規
―ひゃくじょうせいき―
長蘆宗賾
―ちょうろ・そうさく―
清規
―せいき―
叢林
―そうりん―
禅僧
―ぜんそう―
道元
―どうげん―
明全
―みょうぜん―
永平寺
―えいへいじ― 曹洞宗の大本山で、『道元』が建長5年(1253年)に開創。坐禅と規律を重んじる修行の場であり、茶を用いた「茶礼」も日常の一部として取り入れられた。
曹洞宗
―そうとうしゅう―
紫野
―むらさきのりんざいしゅう―
大徳寺
―だいとくじ― 京都・紫野に位置する臨済宗大徳寺派の大本山。『宗峰妙超』によって開かれた禅寺であり、のちに千利休ら茶人たちとの交流を通じて茶道文化の中心的存在となる。
宗峰妙超
―しゅうほう・みょうちょう―
南浦紹明
―なんぽ・じょうみょう― 南北朝時代に『虎関師錬』によって著された往来物。礼法や知識をまとめた教養書であり、当時の銘茶産地が記されている。寺院を中心とした茶園の広がりや、各地における茶文化の浸透を裏付ける資料のひとつ。
禅宗寺院
―ぜんしゅうじいん―
鎌倉幕府
―かまくらばくふ―
将軍
―しょうぐん―
源実朝
―みなもとの・よりとも―
禅宗
―ぜんしゅう―