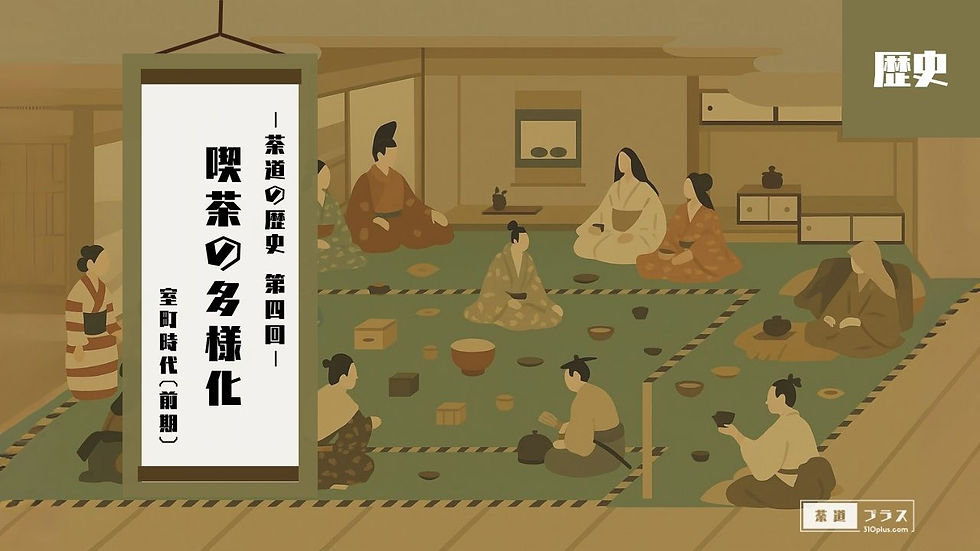3-5|喫茶の転換期 ~庶民と茶の距離が近づくとき~|第3回 喫茶のはじまり|鎌倉時代|茶道の歴史
- ewatanabe1952
- 2023年1月20日
- 読了時間: 3分
更新日:7月21日
全10回
茶道の歴史
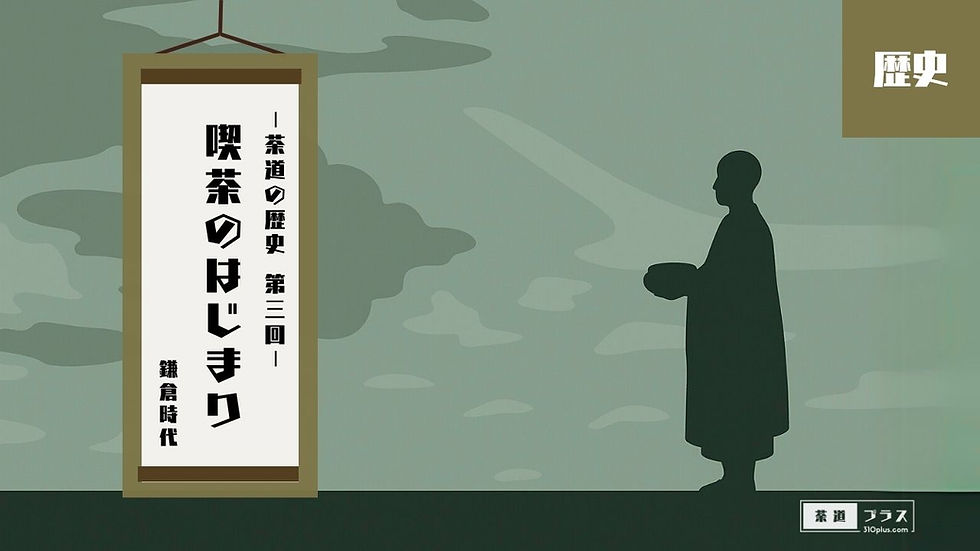
茶の役割
薬か、それとも嗜好品か――。
“茶”はその役割を変えながら、人々の暮らしの中に静かに浸透していきました。
寺院や武家に限られていた“茶”が、やがて庶民の手にも届くようになる過程には、ある逸話が語り継がれています。
今回は、“茶”が文化として広まる転換点を、物語とともに紐解きます。
『沙石集』に見える庶民と茶の接点

鎌倉時代(1185年-1333年)後期、“茶”は武家や禅僧**の間に広く浸透し始めていました。
やがてこの文化は、寺院の外へと少しずつ広がり、民衆の関心を集めるようになります。
その様子は鎌倉時代後期の弘安六年(1283年)に「無住道暁*」により編纂された仏教説話集**『沙石集**』に、牛飼いが僧侶の飲む茶に興味を示した一話がみえる。
ある日、牛飼いは禅僧が茶を喫すところを覗き見し
❝❝❝
私にももらえないか?
❞❞❞
と禅僧に尋ねたところ禅僧はこう答えます
❝❝❝
茶というのは三つの徳がある薬であり、 その一つは“眠気覚まし” その二つは“体内消化” その三つは“性欲抑制” である。
❞❞❞
するとこの話を聞いた牛飼いは
❝❝❝
そんな薬は結構です
❞❞❞
とその場から立ち去ったといいます。
この逸話は、単なる寓話**ではなく、薬や修行の補助として限られた場で用いられていた“茶”が、一般民衆の目にも触れるようになっていたことを示す貴重な史料といえます。
つまり今まで寺院や武家社会に限られていた“茶”が一般民衆の間にも広がっていることを示唆しています。
庶民化と茶文化の広がり

こうして、“茶”は“薬”としての実用性と、“嗜好品”としての楽しみの間を揺れ動きながら、次第に日本全土に広まっていきました。
やがてこの喫茶文化は、室町時代(1336年-1573年)にはいると―茶寄合**―、―闘茶**―へと発展し、やがて―茶の湯文化―の成立へとつながっていくこととなります。
一碗に宿る文化の転換点
“茶”が薬から嗜好へと変化する過程には、人々の暮らしと心の移り変わりが映し出されています。
一碗の“茶”が、ただの健康飲料に留まらず、やがて文化や遊びへと昇華していくその軌跡は、私たちの日常にもどこか重なるものがあります。
次回は、“茶寄合”、“闘茶”など、遊芸としての喫茶へと進化する姿をご紹介します。
登場人物
無住道暁
1227年―1312年|大円国師|僧|臨済宗|「長母寺」開山|「沙石集」の著者|
用語解説
禅僧
―ぜんそう―
無住道暁
―むじゅう・どうぎょう―
仏教説話集
―ぶっきょうせつわしゅう―
沙石集
―しゃせきしゅう―
寓話
―ぐうわ―
茶寄合
―ちゃよりあい―
闘茶
―とうちゃ―