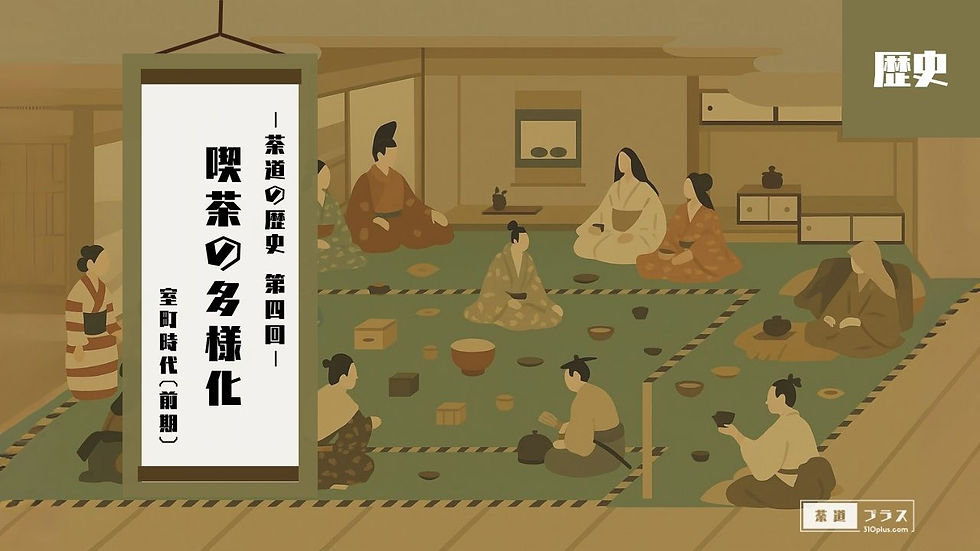3-8|一碗の勝負 ~闘茶に熱狂した人びと~|第3回 喫茶のはじまり|鎌倉時代|茶道の歴史
- ewatanabe1952
- 2023年1月23日
- 読了時間: 4分
更新日:7月21日
全10回
茶道の歴史
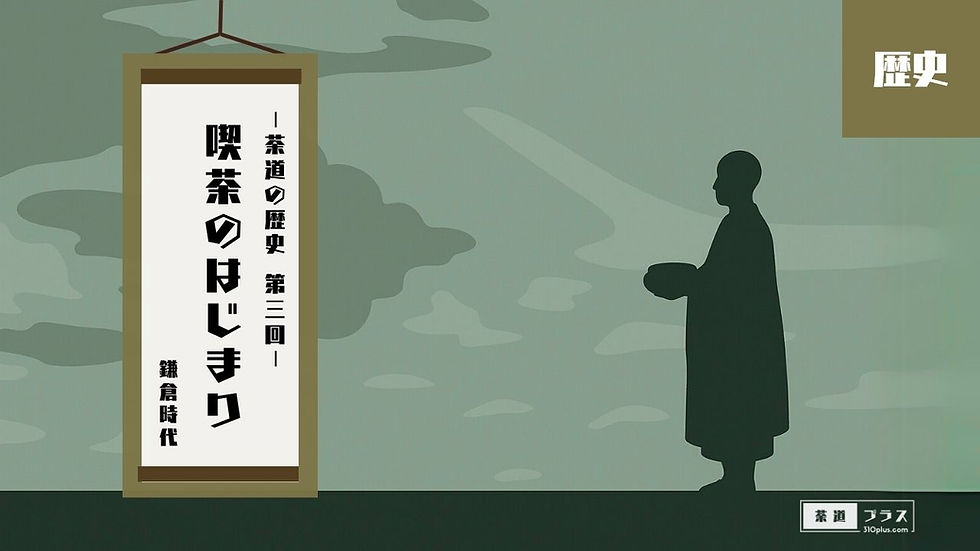
勝負の道具となった一碗
“茶”は、心を調えるもの――それだけではありませんでした。
しかし、その香りや味を競い合い、いつしか“茶”は―“勝負の道具”―となってゆきます。
当時の人はなぜ、ただの一碗に熱狂したのか?
今回は、鎌倉時代(1185年-1333年)末期から南北朝時代(1337年-1392年)にかけて流行した―闘茶**―の世界をひも解きます。
闘水から闘茶へ

前項で触れた喫茶文化の確立にともない、鎌倉時代(1185年―1333年)末期から南北朝時代(1337年―1392年)にかけて、“茶”はさまざまな形で楽しまれるようになります。
そのひとつが、飲んだ茶の産地や品質を当てる遊戯―“闘茶”―でした。
当時、飲んだ“水”の産地を当てる遊戯である―“闘水”―が流行しており、その発展として“茶”を飲み比べ“本茶**”か“非茶**”かを当てるという、単純な娯楽として武士の間で始まりました。
ルールの発展と豪華な賞品

初期には栄西*が京都・栂尾の「高山寺**」の華厳宗**中興の祖と称される明恵*に譲った茶を―“本茶”―とし、それ以外の産地の“茶”を―“非茶”―として飲み当てる簡素な遊びでした。
しかし次代が下がるにつれルールは複雑化し、―何産の茶か?―を当てる銘柄当ての形式や、点数制を導入した勝負形式も登場。
時には数日にわたって開催され、“砂金”“刀”“唐物”など高価な賞品が賭けられることもありました。
なかでも、贅沢を好み、豪華な景品をかけた佐々木道誉*の―“闘茶会”―の様子は南北朝時代(1337年―1392年)に記された四十巻からなる『太平記*』に詳しく描かれています。
佐々木道誉は華麗・贅沢を好む『婆娑羅(バサラ)大名*』と知られ、常識にとらわれない独特の美意識を体現した人物として広く知られていました。
やがて―“闘茶”―は貴族や武士だけの遊戯から庶民にまで広く流行するようになります。
禁止令と文化への定着

しかし、―“闘茶”―のあまりの熱狂ぶりを受け、室町幕府**の初代将軍**・足利尊氏*は建武三年(1336年)十一月七日に政治方針を定めた『建武式目*』の中で
❝❝❝
―原文― 諸国司以下、濫妨狼藉、闘茶、博奕等、停止せしむべき事 ―現代訳― 諸国の国司**以下の者たちは、勝手気ままな振る舞いや乱暴、闘茶、賭博などを禁止すべきであること。
❞❞❞
として禁止するが、―“闘茶”―の人気は衰えることなく、なんとその後100年以上にわたって続けられ、“茶の湯”の一形態として茶文化の中に深く根を下ろしていこととなります。
茶の湯への胎動
一碗の“茶”をめぐる興じと勝負——そこには、人の欲と美意識とが交差する、奥深い文化の一面が伺えます。
“茶”という静かな存在が、人々の熱狂と欲望の的となった―“闘茶”―。
その文化の奥には、遊戯を通じて育まれた審美眼と、やがて成立する“茶の湯”への胎動がありました。
次回は、この―“闘茶”―を超えて、精神性と礼法を重んじる―“書院茶**”―の世界をひも解きます。
登場人物
栄西
1141年―1215年|明庵栄西|僧|臨済宗開祖|「建仁寺」開山|
明恵
1173年―1232年|明恵上人|僧|華厳宗中興の祖|栂尾山「高山寺」開山|
佐々木道誉
1296年―1306年|武将|守護大名|バサラ大名|
足利尊氏
1305年―1358年|武将|征夷大将軍|室町幕府初代将軍|
用語解説
闘茶
―とうちゃ―
本茶
―ほんちゃ―
非茶
―ひちゃ―
高山寺
―こうさんじ―
華厳宗
―けごんしゅう―
太平記
―たいへいき― 南北朝時代の動乱を描いた軍記物語。全40巻。作者は未詳ながら、貴族や武士の逸話、戦乱、風俗などを広く伝える貴重な史料。『佐々木道誉』の華麗な「闘茶会」の描写でも知られる。
婆娑羅大名
―ばさらだいみょう― 「バサラ」とは主に南北朝時代(1336年-1392年)の社会風潮や文化的流行をあらわす言葉であり、当時の流行語「異風異体」とも呼ばれ奇抜なものを好む美意識をいう。特に佐々木道誉は「バサラ大名」の象徴的な存在で、放埒、傲慢な常軌を逸した数多くの奇行が伝えられている。
足利尊氏
―あしかが・たかうじ― 室町幕府を開いた初代将軍で、南北朝時代の動乱を導いた武将。後醍醐天皇の建武の新政に反旗を翻し、1338年に征夷大将軍に任ぜられました。京都に幕府を開き、武家政権を再興しましたが、南朝との対立や内部の抗争に苦しみました。禅宗を深く信仰し、建仁寺や天龍寺などの保護を通じて文化の振興にも貢献しました。
建武式目
―けんむしきもく― 建武三年(1336年)十一月七日に室町幕府初代将軍『足利尊氏』が制定した政治指針。全17条から成り、第7条で「闘茶の禁止」を明記。喫茶が社会に広く浸透し、秩序を乱すほどの影響力を持っていたことがうかがえる。
書院茶湯
―しょいんちゃゆ―