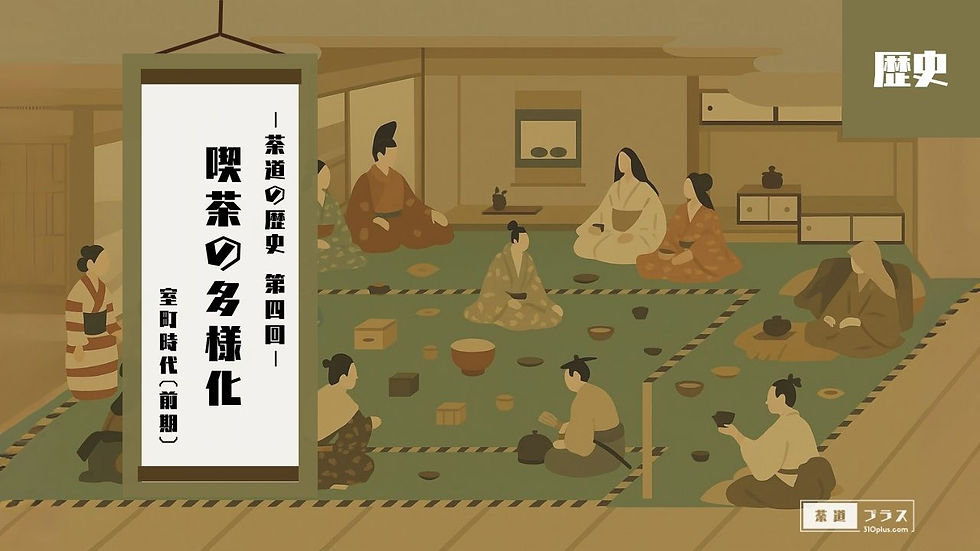4-2|茶会の誕生 ~畳とともに始まる茶の芸術~|第4回 喫茶の多様化|室町時代(前期)|茶道の歴史
- ewatanabe1952
- 2023年1月27日
- 読了時間: 2分
更新日:7月21日
全10回
茶道の歴史

茶はどこで飲まれていたのか
“茶”は、どこで、どのように飲まれていたのでしょうか。
人が集う場に茶があり、空間と共に文化が育まれていった——―。
それは、やがて―“茶会”―として様式を持ちはじめます。
今回は、“茶会”のはじまりと空間の変遷をたどります。
北山文化と「会所」の出現
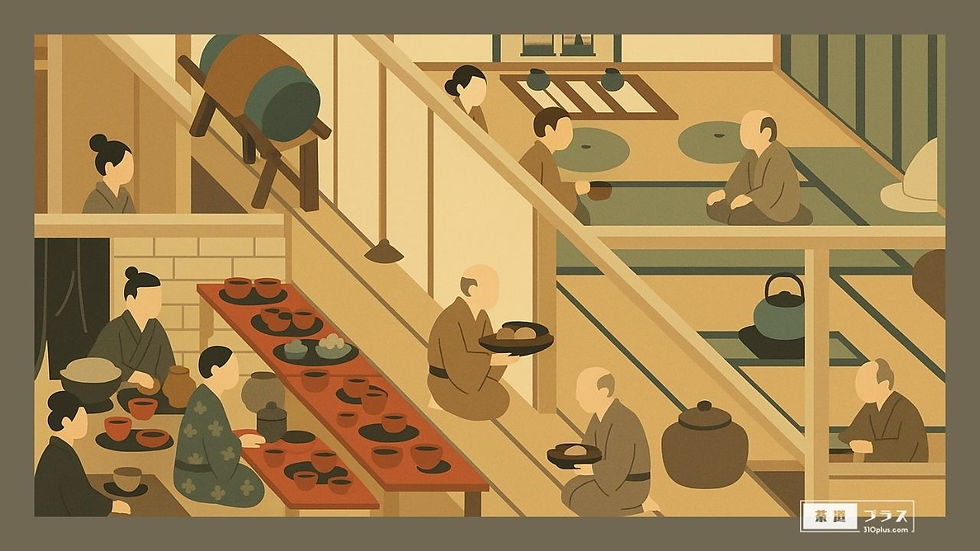
室町時代(1336年-1573年)の初期、北山文化**の開花とともに、将軍や大名たちの間で“茶”を中心とした宴会が開かれるようになります。
これがのちに―“茶会”―の原点とされています。
当時、彼らは「会所**」と呼ばれる専用の建物を設け、“茶”を振る舞う空間として活用していました。
「会所」には、唐物絵画や墨蹟**、名品とされる茶道具などが飾られ、それらを鑑賞しながら、別室の「茶点所**」で点てられた茶を愉しんだと記録されています。
当初は板敷の空間に椅子を設け、そこに座して喫茶を行っていましたが、時代の変化とともに畳が敷かれるようになり、茶を取り巻く空間に大きな変化が起こります。
やがて「会所飾り**」と呼ばれる座敷内の装飾方法が整えられ、茶の場が一層形式を帯びていくこととなります。
茶の場がもたらした新たな文化

このように、“茶”は単なる薬や嗜好品としての役割を超え、空間や作法をともなった文化へと成長していきます。
そしてその過程で、礼法や思想と融合しながら、その後の―“茶の湯”―へとつながる礎が築かれていくこととなります。
“茶”を味わう場所が整えられ、人と文化が交差する中で、“茶”は―“空間芸術”―としての歩みをはじめていたことがわかる。
“茶の湯”は、単なる飲食の場ではなく、様式・芸術・精神性が交錯する“舞台”となっていきました。
空間と所作が一体となることで、“茶”は新たな文化の核を形づくり始めます。
次回は、そこに美意識を注ぎ込み、新たな茶風を生み出した村田珠光*の登場に迫ります。
登場人物
村田珠光|
………
用語解説
0
――
0
――
0
――
0
――
北山文化
―きたやまぶんか―
会所
―かいしょ―
墨蹟
―ぼくせき―
茶点所
―ちゃてんどころ―
会所飾り
―かいしょかざり―
0
――
0
――
0
――